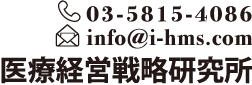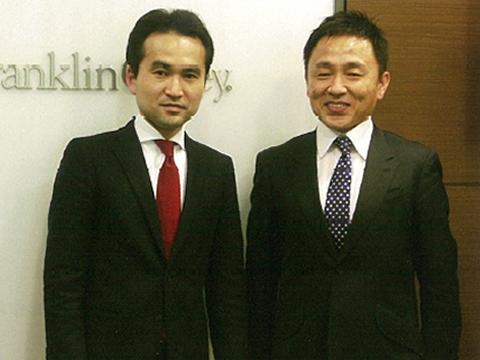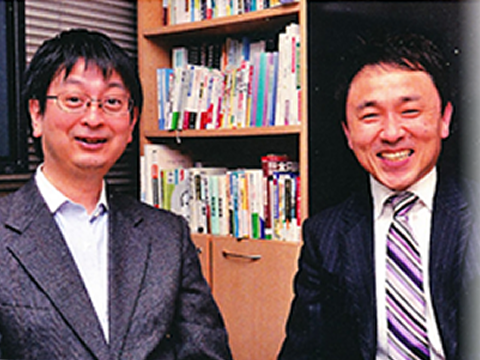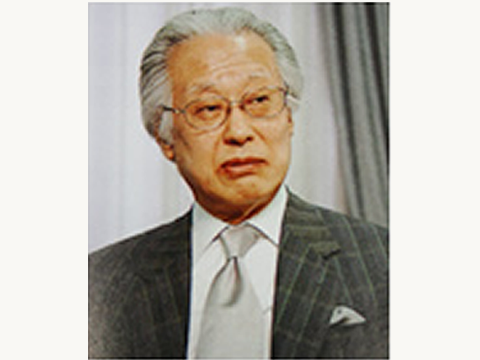2.クレドを定着させる条件
核心はリーダーの条件
- 櫻堂
-
日本でもクレドがブームになっていますが、せっかく作ったのにうまく機能しなかったという話をよく聞きます。組織の理念が単なるお飾りになったのではどうもうまく行きません。つまり、クレドを作成することが目的ではなく、このクレドをどのように浸透させるのかという難しい課題があるわけです。実はこれが出来なければ何の意味も成さないわけです。
「私たちは患者様のために最高の医療を提供します」とどこの病院の理念にもうたわれていますが、本当にそうなのかと疑われる現実があります。高野さんの本を読んで「これだ!」と思ったのは、毎日の朝礼でクレドについてディスカッションンしているというお話です。
- 高野
-
クレドを浸透させるには二つの条件があると思います。一つは、リーダーの心の位置、あるいはドメイン(活動領域)です。最近の医療は、このドメインがわかりにくくなっているような気がします。
私の母は病気で亡くなりましたが、最後は一人の医師に全てを託すことができました。それはその医師の「俺以外にお母さんを預けられるところはない」という圧倒的な迫力が伝わってきたからでした。「他の病院より施設は小さいし設備も古いが、職員の心意気は一級だし、俺の腕だって馬鹿にしたものじゃない。今の日本では、どの病院も当院より適切に診られる施設はない」と断言しました。彼のパッションに触れた私は、「先生にお願いします」とすべてを任せることができたのです。
- 櫻堂
-
リーダーが方向性をしっかり持っているかどうか、そして情熱をもって語れるかどうかということですね。
- 高野
-
そう思います。人は、仕切られるととても心地よいものです。レストランの信頼できる支配人に、「今日は大事なお客だからよろしく」と言うと、「好みもすべて存じ上げていますからお任せください」と応えられると、とても安心できます。これは“仕切り”です。一方、「今日はこれとこれがおいしいですから、ぜひ召し上がってください」と、相手の都合でコントロールされるのは違うのです。
日本企業のトップの多くは、失敗したときの責任を回避したがる、いわば後輪駆動型です。しかしアメリカのトップマネジメントでは、トップ自らがリーダーシップを発揮する前輪駆動型でなければ評価されません。
クレドを定着させるもう一つの条件は、従業員が十分納得した内容であることです。 経営者が組織の理念を機械的にあてはめて一方的に作ったクレドと、 プロジェクトを組織して、10年後、20年後の組織の姿を思う存分描いてもらってできたクレドではずいぶん違います。
あるメーカーでは、20代の女子社員3人を担当にして、軽井沢のホテルに2週間滞在させて、自由に原案を考えさせました。若い社員の発想がふんだんに盛り込まれたすばらしいクレドが出来上がりました。
このように、クレドを形にするときのプロセスがとても大事なのです。経営者が作ると、どうしても会社都合が入ってしまいますが、現場で常にお客様と接している従業員が考えると、お客様都合で考えることができます。
例えば、お酒を飲んだ翌朝は、ホテルの朝食より、夜食メニューにある蕎麦を軽く食べてチェックアウトしたい場合がありますが、材料さえあれば難しいことではありません。もし、「承知しました」と言われたら、それだけで一日元気に過ごせます。 会社の決まりだし、調理場にはいやな顔をされるから、「ノー」と言っても罪にはならないからです。これは会社都合の典型です。
お客様と接点が多い従業員が作ったクレドなら、お客様都合の言葉が入ってきます。 クレドは会社と従業員の宣誓書ですから、現場が受けたのにキッチンが「ノー」とは言えません。お客様は要望が叶って嬉しいし、従業員にも仕事の張合いになります。“気持ちのスイッチ”を入れる効果があるのです。
- 櫻堂
-

日本人は組織の都合で動くシステムの中で生きています。リッツ・カールトンは従業員のためにあるとおっしゃいましたが、ほとんどの医療機関にはそうした発想はありません。病気を治すところだから、理念には「患者さんのために・・・・・」と書いてあり、そのためにサーバント的に働くと言う意識が強い。
また、医師を中心にシステムが動いているので、「患者様」と言いながら、深層心理には「患者を診てやる」「病気を治してやる」という意識があるからどうしても上下の関係ができてしまう。私は「マスター・サーバント・システム」と呼んでいますが、気持ちの奥底にそうした意識があるから、「患者様」と言っても本心はそこにない。これが医療提供者都合の弊害です。